Karl RICHTER リヒター
プロフィール
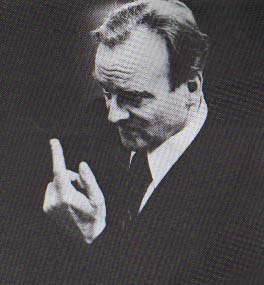 1926年10月15日、ザクセンのブラウエンにて牧師の息子として生まれる。
1926年10月15日、ザクセンのブラウエンにて牧師の息子として生まれる。
11歳でドレスデンの聖十字架教会付属学校に入るとともに、そこの聖歌隊のメンバーとなった。この聖歌隊は、宗教音楽においてシュッツやバッハ以来の長い歴史と伝統を誇る、ドイツでも第一線級のものであり、ワーグナーもここのメンバーであった。
1946年、ライプツィヒに移り、国立音楽大学で学ぶ。
1949年、演奏家資格試験に合格するとともに、聖トマス教会のオルガニストに就任。この間、シュトラウベとラミンという、現代のバッハ演奏の基盤を確立した名手に師事をし、彼らの指揮の元でチェンバロとオルガン演奏も行っている。
1951年よりミュンヘンに移り住み、ミュンヘン音楽大学の講師を務めた後、1956年に教授に任命された。この間、聖マルコ教会のオルガニストも兼ねている。
一方、宗教音楽演奏のためにアマチュアを中心とした合唱団「ハインリッヒ・シュッツ合唱団」を立ち上げる。1953年に、これをミュンヘン・バッハ合唱団へと拡大、1955年に同管弦楽団を組織し、指揮者としても精力的な活動を始め、ミュンヘンをバッハ演奏の中心地にまで引き上げた。
1956年、アンスバッハのバッハ音楽祭芸術監督を務める。
1964年、ミュンヘン市より「芸術奨励賞」を与えられる。
リヒターとミュンヘン・バッハ合唱団・同管弦楽団は、ミュンヘンにとどまることなく世界各地に演奏旅行を敢行し、敬虔な信仰に裏打ちされたバッハの極めて高い精神性を隈無く表現して、現代における世界最高のバッハ指揮者として名声を恣にしたのである。
1969年に来日し、マタイ受難曲とミサ曲ロ短調という宗教音楽の大作を日本の聴衆に聴かせるとともに、オルガンとチェンバロのリサイタルも開いて、大きな感銘を与えた。
そして、1981年の春、2度目の来日を直前に控えた2月15日、心臓発作のためミュンヘンで急逝。
世界のバッハファンは落胆の渕にたたき落とされたのであった。
断片的な印象
リヒター急逝の衝撃は、いまでも記憶に残っている。ベームに引き続き、クラシックファンはそのかけがえのない才能の遺失を惜しんでいた。
私は、言いようのない憤りを感じていた。来日を一日千秋の想いで待ち望んでいたのに酷すぎるではないか。
あまりにも早い、早すぎる死ではないか、と。
あるいは、あまりにも神に愛された故なのだろうか、などと。
リヒターは、現代の楽器編成(合唱技法も含む)によるバッハ演奏において、一つの頂点を形作った。
バッハの宗教音楽の演奏を目指す殆どの演奏団体が、リヒターの表現方法を理想としていることは、まさに当然の帰結であるように思う。
前述したミュンヘンバッハ合唱団などを組織するにあたってリヒターは、自ら街頭に立ちビラ配りをして団員の募集をしたという。
リヒターがプロに拘らなかったのは、おそらく、宗教音楽の演奏に最も大切なのは、その音楽の中に込められた神へのメッセージを虚心坦懐に受け止めることのできる敬虔な信仰心と感受性だと考えたからではないだろうか。私は、キリスト者ではないが、マタイ受難曲の演奏に関わってきた経験から推し量るに、一番大切な部分はその歌詞などに込められているバッハの信仰への形ではないかと思ったものである。
そのリヒターの思いが、あの厳しくも感動的な演奏につながっている。
しかし、リヒターは啻に棒を飲んだような態度でバッハの演奏に立ち会っているのではない。
宗教音楽を離れたリヒターの、例えばオルガン演奏などの自在な表現力を見よ。
私は特に、死の直前に録音された、ペーター・シュライヤーとの「シュメッリ讃歌」に強い印象を持っている。
ここでのリヒターはオルガンによる伴奏を担当しているのだが、通奏低音の譜で書かれたものを様々に変奏して、めくるめく官能的な表現を現出している。特に私の印象に残っているのは、第3曲「Ich steh an deiner Krippen hier」の伴奏だ。
是非とも多くの人に聴いていただきたいと思う。フライベルグのジルベルマン・オルガンから流れる自在な音のうねりは、新しいリヒターの魅力を余すところ無く伝えている。
しかし、それだけに失ったもののあまりの大きさを思い知る。あまりに悲しすぎてやりきれない。
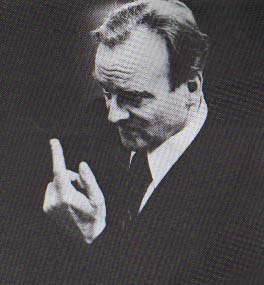 1926年10月15日、ザクセンのブラウエンにて牧師の息子として生まれる。
1926年10月15日、ザクセンのブラウエンにて牧師の息子として生まれる。